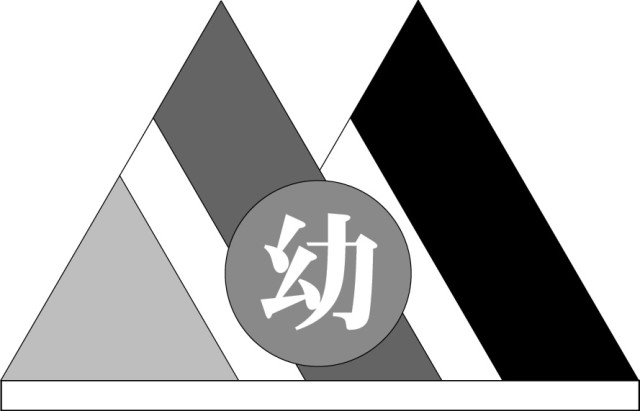堺市立みはら大地幼稚園
来年度の入園も含め、入園は随時受け付けております。
希望される方は、まずは幼稚園(072-361-8772)にご連絡ください。
入園願を提出された方は、12/12(金)の午後に入園前健康診断を行います。
郵送または配信されたお知らせをご確認ください。
研究実践
-
3歳 公開保育の様子①
- 公開日
- 2025/11/18
- 更新日
- 2025/11/18
研究実践
3歳うさぎ組・きりん組で公開保育を行いました。
思い思いに遊ぶ子どもたちの様子を参加者の皆さんに見ていただきました。
うさぎ組のお部屋の近くでは、といをつなげてどんぐりを転がして遊ぶ子どもたち。
いつもはぶどう組さんが遊んでいるのにまぜてもらうことが多いですが、今日はぶどう組さんがいません。
3歳の子どもたちだけで上手にといをつないで、どんぐりの道を作っていました。
たくさん並んだどんぐりから「どれにしようかな?」と真剣な表情で、
形や大きさを比べながら自分のお気に入りの1個を選んでいました。
1つずつ転がしては、どんぐりが転がる音を楽しんでいました。
たくさん集めて一気に転がして遊ぶ子もいて、楽しみ方もそれぞれのようです。
きりん組のお部屋の前には、レストランや水槽で遊ぶ子どもたちがたくさん。
葉っぱや木の実を使ってレストランごっこを楽しんでいました。
泡をクリームに見立ててジュースやパフェをつくったり、
泡の入った鍋をチャーハンだといって動かしたり。
鍋をふる様子は、お母さんゆずりなのかな。絶妙な手つきで真剣そのもの。
他にも、葉っぱやどんぐり、柿の実などをきれいに盛り付けてケーキづくりをしたり、
水槽に入れた葉っぱを網で焼いて魚だよといって食べさせてくれる子どもたちもいました。
子どもたちの想像力は豊かです。
自然の素材を活用しながらごっこ遊びを思いっきり楽しんでしました。
-
3歳 公開保育の様子②
- 公開日
- 2025/11/18
- 更新日
- 2025/11/18
研究実践
今日は、風が強く、森の広場にたくさんの落ち葉が…。
自然の変化に気づいた子どもたちが、落ち葉を拾っては散らし、拾っては散らし、何度も繰り返していました。
落ち葉が舞う様子や落ち葉の落ちる音を楽しんでいました。
虫探しチームは、お目当てのバッタは見つかりませんでしたが、畑の大根の葉に小さな芋虫を発見!「いたよ!」と嬉しそうに友だちと見せ合いっこ。
他にも、砂場で大きな山を作って遊ぶ子、森の小屋でアイスクリーム屋さんを開いて遊ぶ子もいました。
丸太わたりに挑戦する子どもたちや、作ったジュースを木のストローで吸っては「おいしい!」と笑顔を見せてくれる子もいました。
今日の午後は、3歳の子どもたちが森を独占。4・5歳さんのいない中、思いっきり遊ぶ様子が見られました。
遊びの後は、みんなで今日の楽しかったことを振り返って、また明日遊ぼうねと約束しました。
-
公開保育討議会①
- 公開日
- 2025/11/18
- 更新日
- 2025/11/18
研究実践
+1
保育後には、研究討議会を行いました。堺市の様々な幼児教育施設から先生方が公開保育に参加してくださいました。本園からは、これまでの3歳の遊びの様子や環境設定などについて参加者の皆様に説明させていただきました。その後、2グループに分かれて、参観していただいた中での気づきや感想を話し合いました。参加者の皆様からは、子どもたちが日々の自然の移り変わりを遊びに取り入れながら遊ぶ様子や自分の大好きな居場所を見つけて遊ぶ様子について感想やご意見をいただきました。
-
公開保育討議会②
- 公開日
- 2025/11/18
- 更新日
- 2025/11/18
研究実践
+1
各グループで出た意見は、全体で共有しました。参加者のみなさんから、たくさん感想やご意見をいただきました。今後の参考にさせていただきます。助言者としてご参加くださった、常磐会短期大学 中村妙子先生より、本園の研究実践について指導講評をいただきました。「日々の自然の変化を遊びに取り入れた秋しかできない遊びが展開されていた」「3歳の子どもたちは大好きな先生がそばにいること、大好きな自分の居場所があることが大切」「先生は子どもと環境をつなぐ役割、子どもの思いを信じて待つことが大切」「繰り返し遊ぶ中で、子どもたちの気づきや遊びの広がりが生まれる」など、今後の保育に活かせるお話をたくさん教えていただきました。学びが深まる、充実した時間となりました。
ありがとうございました。
-
5歳 公開保育の様子①
- 公開日
- 2025/11/07
- 更新日
- 2025/11/07
研究実践
5歳ばら組で公開保育を行いました。
みはら大地幼稚園の広い園庭を使って、思い思いに遊ぶ子どもたちの姿を
堺市の様々な幼児教育施設や小学校の先生方に見ていただきました。
以下、公開保育の様子です。
おはよう広場では、子どもたちが柿とりに夢中になっていました。
それぞれに試行錯誤しながら作った道具をつかって、上手に柿を取っていました。
森のお家の中では、さら砂づくりをしている二人がいました。
できたさら砂は秘密の場所にしまっているようです。二人だけの世界に夢中です。
森のキッチンで遊ぶ子どもたちは、なにやら、掘ったり、畑を作ったり、お料理したり…。
遊ぶうちに幼虫を見つけて大喜びでした。
-
5歳 公開保育の様子②
- 公開日
- 2025/11/07
- 更新日
- 2025/11/07
研究実践
子どもたちの発想は、本当に豊かですね✨テラスでは、3つのグループが、何やら制作中。
一つ目は、舞台のようなものを作っているグループ。
思い思いに制作をしていたかと思うと、
「始めるよ!」と一人が声かけをし、人形劇が始まりました。
公開保育を見に来てくださった先生方をお客様にして、ペープサートの劇をしていました。
相談しながら二人で作っていたのは、なんと「かまきりの迷路」。
つかまえたかまきりが遊ぶための迷路なんだそうです。
かまきりさんもびっくりです😧
マインクラフトの世界を表現しようとがんばる子どもたちもいました。
手や足に絵の具をつけながら一生懸命につくっていたものが、でき上っていました。
-
5歳 公開保育の様子③
- 公開日
- 2025/11/07
- 更新日
- 2025/11/07
研究実践
一輪車の練習をする子どもたちもいましたよ。
運動会でお友だちの演技を見て、自分もやりたいとがんばっている様子です😊
しばらくすると、だれかの号令で野球が始まりました。
打って、走って、キャッチして、大忙し。
応援してくれるお友だちも集まってきて、とっても楽しそうでした🎶
遊びが終わって、保育室に戻るとみんなでふりかえりの時間です。どんな遊びをしたのか、どんなことが楽しかったのか、それぞれの思いを共有していきます。お友だちの話を聞いて、「月曜日は何しようかな?」と考えるのかな。来週も、みんなでたくさん遊べるといいですね。5歳の保護者の皆様、公開保育にご協力いただきありがとうございました。ばら組の子どもたちのすてきな姿、いろいろな先生方に見ていただくことができました。職員一同、公開保育で学んだことを今後の保育に活かしていきますね。
-
公開保育討議会①
- 公開日
- 2025/11/07
- 更新日
- 2025/11/07
研究実践
保育後には、研究討議会を行いました。堺市の様々な幼児教育施設や小学校などから先生方が公開保育に参加してくださいました。本園からは、これまでの遊びの広がりや友だち同士のつながり、環境設定などについて参加者の皆様に説明させていただきました。その後、2グループに分かれて参観していただいた中での気づきや感想を話し合いました。参加者の皆様からは、子どもたちが自然の素材を十分に活かして遊ぶ様子や子どもたち同士で工夫しながら遊ぶ様子について感想やご意見をいただきました。いただいたご意見は、今後の保育の参考にさせていただきたいと思います。
-
公開保育討議会②
- 公開日
- 2025/11/07
- 更新日
- 2025/11/07
研究実践
+2
各グループで出た意見は、全体で共有しました。・教師に対して「見て見て!」「手伝って」というのではなく、子どもたち同士で相談し合う姿が見られた。・大人がヒヤッとするような道具を上手に扱う姿を見て、経験を積むことが大切だと感じた。・子どもたち同士で役割を決めて遊ぶことができるのは、5歳ならではの姿だと感じた。・一人ひとり別々に作っていたのが、だれかの「始めるよ!」のかけ声で、一斉に集まって始まる様子が見られた。・子どもが悩んでいるときに寄り添う教師の姿が、子どもの自信につながっていると感じた。・ふりかえりで、全員が意見を言うことができるのは、しっかりと遊びこむことができているからではないか。助言者としてご参加くださった、常磐会短期大学 中村妙子先生より、本園の研究実践について指導講評をいただきました。「保育は、子ども理解から始まる」「子どもたちの遊びの中にも、5歳時の育ちを見通した教師のねらいが入っていることが大切」「自然物を取り入れる保育は、子どもたちの感覚を呼び覚まし、思いを表現させる」「子ども同士の関わり育てることで、皆が輝く保育を実践することができる」など、今後の保育に活かせるお話をたくさん教えていただきました。学びが深まる、充実した時間となりました。
ありがとうございました。
-
公開保育討議会②
- 公開日
- 2025/06/24
- 更新日
- 2025/06/24
研究実践
常磐会短期大学 中村妙子先生より、本園の研究実践について指導講評をいただきました。「幼児教育は目に見えない心を育てる教育であるということ」「させるのではなく、自らする学びの大切さ」「子どものやりたい気持ちを引き出す環境構成の在り方」などについてご講演いただきました。
学びが深まる、充実した時間となりました。
ありがとうございました。