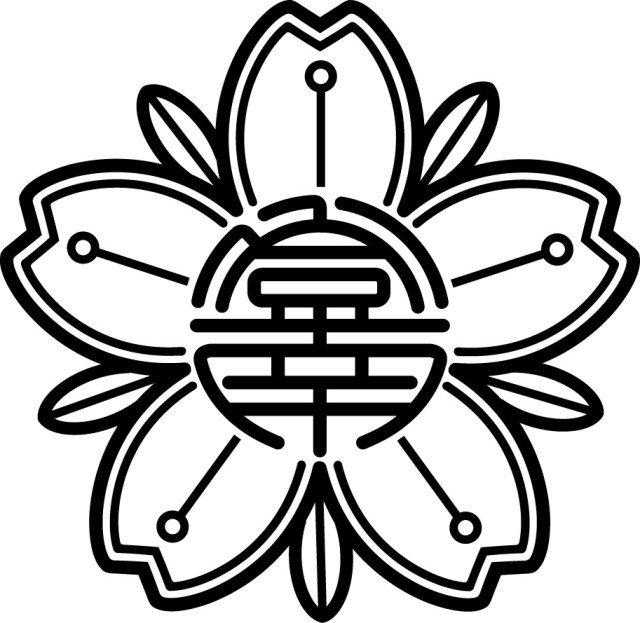堺市立登美丘南小学校
子どもがつくる学校「みんなのとみなみ」
キーワード「自己決定 なかまづくり」
登南の探究的な学び
-
探究的な学び3~問いストーリー~
- 公開日
- 2025/04/30
- 更新日
- 2025/04/30
登南の探究的な学び
6年生の国語「帰り道」の学習です。クラスのみんながもった「問い」から学習計画を立て、学びを進めます。名づけて「問いストーリー」。今日は、文中のたとえにはどんな意味があるのかを考え、話し合いました。鍵になる2つのたとえから、さまざまな読みがうまれていますね。
-
探究的な学び2~先生は伴走者~
- 公開日
- 2025/04/17
- 更新日
- 2025/04/17
登南の探究的な学び
5年生の算数です。いろいろな数を0.001のいくつ分かで表す学習です。
0.005は0.001の5つ分
0.03は0.001の30こ分
0.1は0.001の100こ分
2は0.001の2000こ分
といった学習ですね。0.001をもとにして考えることがとても難しいのですが、子どもたちは自分の言葉で考え方を説明しています。いろいろな子どものいろいろな表現の仕方で子どもたちの理解は深まっていきます。子どもには子どもの言葉の方がよくわかるのかもしれませんね。時間はかかりますが、先生は子どもたちの力を信じ、伴走者として支援することで子どもは自ら学び、成長していきます。
+1
-
探究的な学び1~話し合いのまとめ方や決め方~
- 公開日
- 2025/04/16
- 更新日
- 2025/04/16
登南の探究的な学び
6年生の特別活動です。グループでみんなの考えをまとめたり、決めたりする話し合いができるかどうかは、探究的に学ぶうえでとても大切なポイントです。結果として「決まる」ことに重点をおくのではなく、どのようにまとめるのか、どのように決めるのかを子どもたちが学び、経験していくことが大切です。このような指導や活動によって1年間の学びをより主体的に、対話的にしていくことができます。
-
探究的な学び84~P-1グランプリ~
- 公開日
- 2025/03/13
- 更新日
- 2025/03/13
登南の探究的な学び
6年生の国語の学習です。6年間で学んだことを活かして、「未来の学校」について提案するプレゼンテーションをしました。名づけて「P-1グランプリ」です。審査員に先生方を招いて開始です。もちろん、司会進行も子どもたちです。今まで、どのようにして聞く人に納得してもらうかを探究しながら学びを進めてきました。課題に対して解決策を考え、自分たちの提案のメリットやデメリットを説明する。事実を整理し、資料化して提示する。また、表現を工夫したり、話し方を工夫することで提案に説得力にもたせるといった学びがたくさん詰まっていました。まさに6年間の集大成ですね。
+7
-
探究的な学び83~探究のサイクル~
- 公開日
- 2025/03/05
- 更新日
- 2025/03/05
登南の探究的な学び
4年生の国語「調べて話そう、生活調査隊」の学習です。身のまわりの疑問や興味をもったことについて調査し、調査結果をわかりやすく整理して伝える学習です。探究のサイクル「課題設定→情報収集→整理・分析→まとめ・表現」を子どもたちが意識し、自ら学びを進めていきます。
+3
-
探究的な学び82~感想から学習計画へ~
- 公開日
- 2025/02/21
- 更新日
- 2025/02/21
登南の探究的な学び
6年生の国語「海の命」の学習です。6年間で身につけた力を総動員して学びます。今日は、初発の感想を交流する活動でしたが、子どもたち一人ひとりの感想や疑問が作品の主題にかかわる問いにつながっていました。6年間の学習を通して、物語を読むときに着目すべき視点が共有されているのだなと感じました。
-
探究的な学び81~お手紙を書く~
- 公開日
- 2025/02/21
- 更新日
- 2025/02/21
登南の探究的な学び
4年生の国語「スワンレイクのほとりで」の学習です。単元計画にもあるとおり、学習のゴールは物語の「ココが好き」を言葉にし、作者にお手紙で伝えるというものです。子どもたちが意欲的になる姿が想像できますね。登場人物の経験や心情、作品の主題を読み取っていく必然性が生まれる学習計画ですね。
-
探究的な学び80~自分の問いをもつ~
- 公開日
- 2025/02/20
- 更新日
- 2025/02/20
登南の探究的な学び
4年生の国語「スワンレイクのほとりで」の学習です。今日のめあては「物語の設定をたしかめて、自分の問いをもとう」です。「問いをもつこと」は学習の出発点であり、目的でもあります。しかし、これは簡単なことではありません。何の疑問もわいてこない、感じたことを言葉にできない、また、学ぶに値しない問いであったり、教科の学習内容から外れてしまっていたり・・・
でも、これを何度も繰り返し、友だちと交流することで、教科の見方・考え方にあった学ぶべき問いをもつことができるようになります。そして、それは学び方の引き出しになっていきます。
-
探究的な学び79〜見方・考え方を働かせる〜
- 公開日
- 2025/02/06
- 更新日
- 2025/02/07
登南の探究的な学び
3年生の社会の学習です。自分の親や祖父母に昔の学校について聞き取り調査をしてきた成果について話し合っています。子どもたちは、今自分たちが通っている学校と比較して、その違いに興味津々です。学習において、課題に向かって追求するには「教科の見方・考え方」を働かせることが大切です。社会においては、次のようなことが「見方・考え方」になります。
【社会的事象等の見方や考え方】
・位置や空間的な広がり
・時期や時間の経過
・事象や人々の相互関係に着目する
・事象を比較・分類したり総合したりする(特色)
・国民(人々の)生活と関連付ける(意味)
この学習においては、時期や時間の経過という見方・考え方を働かせて追求しているというわけです。最後に、事務の先生に昔の学校についてお話してもらいました。たくさんの質問が子どもたちから出てきましたよ。
-
探究的な学び78〜自分だけの要約への道〜
- 公開日
- 2025/01/29
- 更新日
- 2025/01/31
登南の探究的な学び
4年生の国語「風船でうちゅうへ」の学習計画です。説明文を使って、要約の仕方を学びます。要約って・・・決して楽しいものではないですよね。でも、この学習計画を見るとなんだか楽しそうです。ネーミング「自分だけの要約への道」!なんだかワクワクしますね。学習を通して何ができるようになるのか、どんなゴールに向かうのかを自覚し、学びを進めることが意欲的に学ぶためのポイントなんでしょうね。