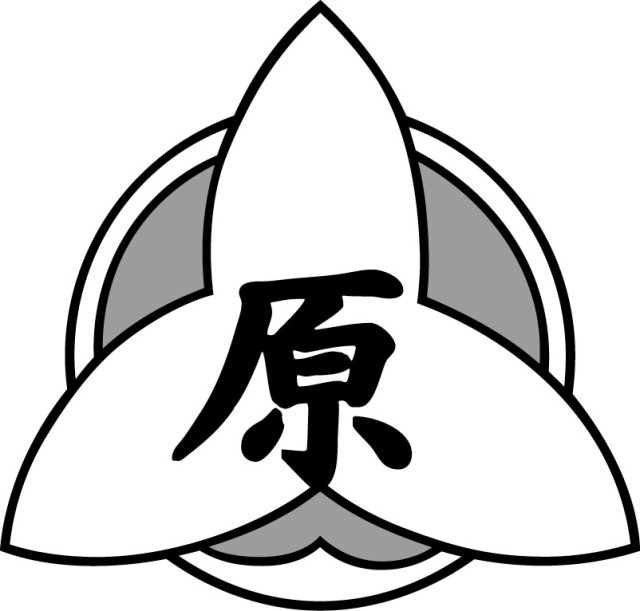1年生のみなさんへ 〜休校中の過ごし方〜 本多先生よりNO.2
- 公開日
- 2020/04/26
- 更新日
- 2020/04/24
1年関係
1年1組担任の本多竜麻です。
休校期間も二ヶ月が経とうとしており、宿題も終わってしまって何をしようかなと思い悩んでいる日々かと思います。本多家でも「今日何をして過ごすか」という問題に頭を抱えています。テレビにも飽きて、スマホにも飽きて、ゲームにも飽きて、この休校期間を何することもなくだらだらと過ごしてしまっていてはもったいないですよね。
そこで、先生はこの期間をいつもより「読書」をしようと思っています。「本を読むのは苦手だなぁ」と感じている人もいるかと思いますので、今日は「読書」についてお話したいと思います。
「読書」は本の世界をただ楽しむだけではなく、すばらしい効果があるのです。
驚くべき読書の効果!!
1 豊かな人間性が育まれる
本の中は疑似体験の宝庫です。物語の登場人物になりきって読み進めたり、書かかれている人の人生に触れることで、日常体験できないことも頭の中で経験することができます。それに伴って、感受性が養われ、世界がより豊かに見えるようになり、想像力・創造力も豊かになってくるとされています。また、コミュニケーション能力も向上します。読書では人の気持ちにも多く触れ、感情を表す言葉をたくさん目にします。そうすることで、周りの人の気持ちをくみとれるようになり、もやもやしていた人の気持ちを周りの人にも伝えられるようになっていきます。成長するきっかけを読書は与えてくれるのです。
2 落ち着いた環境が生まれる
静かな環境で読書をすると、集中力が向上します。また、イギリスの大学の研究で多大なストレス解消効果があると証明されているのです。読書は68%、音楽を聴く61%、コーヒーブレイク54%、散歩42%、ゲーム21%のストレス解消効果があったそうです。
3 「学力」が向上する
本を読むことで、大脳は活性していき、神経回路(=考える力)が発達していきます。また、語彙(ごい)力も向上し、新しい知識や考え方を手に入れることもできます。また、毎月6〜10冊本を読む子は学力が上がるというデータもあります。(←これはなかなかハードルが高いですね。)
そして、先生は読書を通して言葉との出会いを大切にしてほしいと思っています。胸に響く言葉や響きが好きな言葉との出会いは誰しも経験があるのでしょうか。先生が印象に残っている言葉を紹介したいと思います。
一つ目は、伊坂幸太郎さんの「ガソリン生活」の中に出てくる言葉です。
「お手上げの気持ちになった。僕たち自家用車の言葉で言えば、ガルウイングドアの気分だ」
この作品は車視点で話がすすむのですが、イメージがわきましたか?ガルウイングドアを一度検索してみてください。
二つ目は、朝井リョウの「何者」の中に出てくる言葉です。
「自分は自分にしかなれない。痛くてもカッコ悪い今の自分を、理想の自分に近づけることしかできない。みんなそれをわかってるから、痛くてカッコ悪くたってがんばるんだよ。カッコ悪い姿のままあがくんだよ。それ以外に私に残された道なんてないんからだよ。」
みなさんも、「小学生」から「中学生」に肩書きが変わりました。将来は「○○大卒」とか、「○○に留学していた」といった肩書きが手に入るかもしれませんね。でも、肩書きが変わっても、みなさんの内実が変わっていくわけではありません。「小学生」から「中学生」に変わった、みなさんも急激に何かが変わったわけではないかと思います。理想の自分やより高みを目指すには、日々、今の自分を磨いていくしかないのです。
この中学校生活三年間で、ありのままの自分を大好きな人になっていってほしいと思います。そのためにも、一緒に何事にも一生懸命取り組んできましょう。痛くてカッコ悪くたって、頑張っている姿はかっこいい!!みなさんとの学校生活を楽しみにしています。