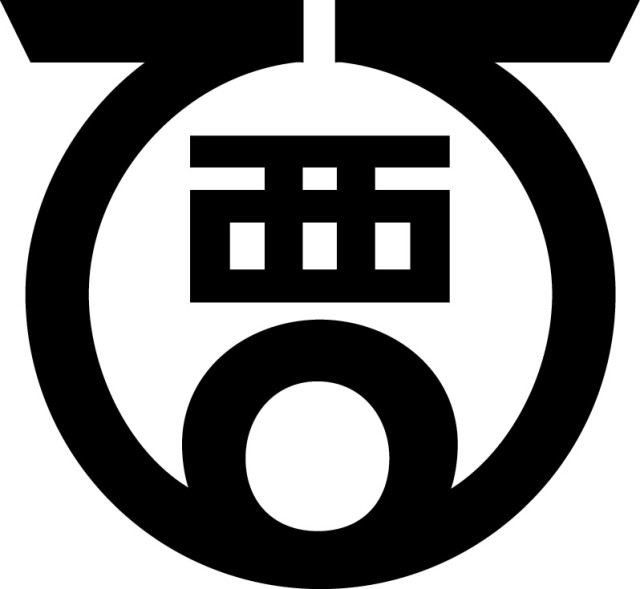月曜日に実施した全校朝礼の内容をまとめました。
今回は「西小の校外学習と学習の効果について」というテーマでお話をしました。
西小の校外学習のよさを学習の定着という視点でわかりやすく説明しました。
先週の金曜日に3・4年生がカップヌードルミュージアム,万博公園,ニフレル方面に校外学習で訪れました。
とても楽しい校外学習となりました。特に4年生が3年生をよくリードしてくれたのが印象的でした。
これで1・2年生の舟渡池公園,5・6年生の奈良公園方面と合わせ,全学年が校外学習を実施したことになります。(3年生は初の貸し切りバス乗車でしたね。)
このように西小の校外学習は,小規模校の利点を生かし,伝統的に2学年が一緒に行くことになっています。その一番いいところは学年の成長がみられることです。低・中・高のそれぞれ上の学年がリーダーシップをとることによって成長が促されています。
そもそも校外学習は学習という言葉がつくように,単なる遊びや観光ではありません。
また,「工場見学や施設見学といった体験学習は,机上で勉強するより学習定着率が高い」とも言われています。
このことは,ある研究結果でも明らかになっていて,「ラーニングピラミッド」という図で一番勉強が身につく方法が段階的に表されているので今日はそれを紹介します。
まず始めの段階は,「人の話を聞く」ことです。授業でいえば先生の話をだまって受け身で授業を聞くことです。
次に学習が身につく方法は,「読書」です。本んを読みながら勉強することです。
その次は,「視聴覚」を利用した勉強です。テレビやタブレット,コンピューター教室での学習にあたります。
その次は,「実演見学(デモンストレーション)」です。先生やインストラクターの実演やお手本を見学することです。
その次は,「グループ議論」です。授業でもよく行うグループで話し合うことです。
その次は,自ら「体験」することです。まさに校外学習で体験すること,そのものです。
そして最後に,一番学習効果が発揮される方法とはなんだか知ってますか?
それは「他者に教える」ことです。授業の中でも教えあい活動はあります。そういえば人に教えるには,いろんなことがわかってないとできないですよね。
そういう視点で西小の校外学習をみてみると,「グループで活動」し,そして「体験」があり,上の学年は下の学年にいろいろ「アドバイス」を行う。ほら,学習にとって身につくことばかりです。さらに,楽しく,みんなの絆も深まるというおまけつきです。
こんな素晴らしい意義のある校外学習ですがそれを成功させるためには,決められたルールをよく守り,学習のめあて(校外学習も「学習」ですから普段の授業とおなじように「めあて」もあります)を理解・意識することが大切です。
次回の校外学習では以上のことも意識して活動してほしいと思います。